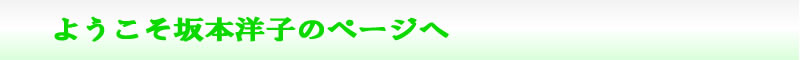著作・メディア
著作・メディア
「私の視点 ウイークエンド ◆ヤコブ病 医療用具被害に救済制度を」
『朝日新聞』朝刊 2002年3月16日(土)掲載
(ウェブ掲載にあたり、『朝日新聞』の許諾を得ています。)
硬膜移植手術でクロイツフェルト・ヤコブ病を発症したとされる患者やその家族が、 国や企業を相手に訴訟を起こした「薬害ヤコブ病裁判」は、和解に向け大詰めを迎えている。 今回の事件が提起した問題は、今後の法整備に大きな示唆を与えてくれる。この事件は、ヒトの組織を使った医療用具による初めての感染被害である。 現在のところ、医療用具による被害は、「医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法」 (以下、機構法という)の救済の対象にはなっていない。 厚生労働省は、医療用具による感染被害はその製造者の責任であり、救済の対象にはならないとしてきた。
そもそもこの法律は、薬害スモン事件を契機に、医薬品を適正に使用したにもかかわらず 副作用被害が発生した場合、被害者の迅速な救済を図るために制定された。 救済には、製造業者の社会的責任に基づいた拠出金が充てられている。
その考え方からすれば、医薬品と同様に、医療用具であっても、適正に使用したが原材料のもつ特性 から未知の病原体が付着または混入し、重篤な疾患にかかるという、 今回のようなケースについても救済されるべきである。
ヒト・動物由来製品による感染被害の救済を盛り込んだ機構法の改正案は、昨年3月に、民主、自由、 共産、社民、無所属の90人により、議員立法として衆議院議長に提出された。
ところが、改正案の付則に裁判で係争中のヤコブ病被害救済を盛り込んだことや、 厚生労働省がヒト由来の医薬品などによる被害救済について、昨年1月に研究会を設置し、 検討を始めたことが影響してか、改正案は審議されることなく、継続扱いとなった。今国会でも、 冒頭に厚生労働委員会に付託されたものの、審議入りはしていない。
一方で、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構は、昨年12月に閣議決定した特殊法人などの 整理合理化計画により、廃止・統合が予定されている。
そうなれば、機構法の改正案は廃案となり、国会での審議さえできなくなってしまう。 次に新たな救済制度をつくる布石にするためにも、一日も早く改正案の審議に入り、 救済制度の必要性について議論しておくべきであろう。ヒト・動物由来製品の開発が進む中、 規制と救済制度の確立は待ったなしである。